
闇に響く呪文、ハム・サ
懐中電灯が光の円錐に吸い込まれ闇になった。
闇は波打ち、からだが激しく引っ張られる。
「座るのよ」
「座るったって」
祐子が富五郎の袖を引き、富五郎は尻を落とした。
地響きが肛門をガンガン突き上げる。地震、雷、世紀末・・・ではない。 無音なのだ。このアンバランスさはなんだろう。
「さぁ、深呼吸しよう」
深呼吸だって?
「ほら、あぐらをかいて!」
裕子も相変わらず謎だ。
富五郎は尻と足を地べたに投げ出し揺れをこらえた。
静寂空間の激しい揺れ。これは宇宙なのか。
祐子の呼吸音が富五郎の鼓膜を震わせはじめた。
ハァァァム、サァァァ、ハァァァム、サァァァ・・
「・・な、なんだよ」
「そうやって呼吸するの。ハァァァムと吸って、サァァァと吐けばいいわ。ゆっくりね」
祐子の声が遠い。いや、近いかもしれない。富五郎の鼓膜を直接触っているかのように感じる。闇の広さがわからない。
「さあ、最初吸って」
ハァァァム、
そして吐く。
サァァァ
ハァァァム、サァァァ
ハァァァム、サァァァ

ところが、どうであろう。呼吸を繰り返すと揺れがおさまりはじめたのだ。祐子の呼吸音も去り、闇は完全に停止した。空間に闇が張り付いている。
富五郎の雑念は揺れとともに去り、意識と眠りが合体しはじめた。
それが本当の眠りだったかどうかはわからない。意識が心とは別の領域に行ったような、眠りさえ超えた感覚だったかもしれない。
洞窟が自分を巻きながら宇宙へ飛び出していく。
夢。そして夢を見る自分を観察するもうひとりの自分がいる。
そばにはカモノタダユキが立っていた。
細身で背が高く、髪は仏陀のような縮れ毛だ。眉は男の指ほどに太く、耳たぶがあごの下まで垂れている。
カモノタダユキが言った。
「からだでもない、こころでもない、もうひとつの存在を見つけるのだ」
「・・・・」
「考えるな」
「・・・」
「この場所は存在の一部ではない。この場所はきっかけだ。感じろ。存在へたどり着く道が見える」
「感じろって・・」
言葉にしたとたん雑念が一気に戻った。
宇宙へ舞い上がろうとしていたからだがすうっと降下していく。
富五郎は汗をかき、怒りさえ充満してきた。
目を開いた。しかし光はない。
「もう、やめてくれ!」
富五郎は叫んだ。
雑念と怒りは闇に波をふたたび起こし、強い力がやってきた。
富五郎の首がぐわっと上へ引っ張られた。
「い、てててえ」
手が上へ下へ激しく動く。千手観音のようだ。
「流れにまかせるがよい」
カモノタダユキが言った。
「まだ存在に近づくのは早い」
「や、やめてくれ」
富五郎の後頭部が直角を超え背中へ曲がっていく。
首が折れてしまう。
「無理だ。やめてくれ!」
富五郎は首からのけぞり、後頭部を激しく地面に打ちつけた。
目の前に星が出て、光が見えた。
ヘルメットの電灯が天井をぼんやりと照らしている。
富五郎は地べたに寝ている。あごを引いて頭を持ち上げると座禅を組んだ祐子がいる。
現実の景色だ。闇の揺れは何だったのだろうか。
「カモノタダユキはどこへ行った」
「カモノタダユキ?」
祐子は座禅を組んだまま、天井をぐるりと見渡した。
「ここ、ただの防空壕じゃないわね。思わずマントラを唱えちゃったわ」
「マ、マントラ??」
「そうしなきゃって思ったのよ。闇がずれたような気がしたし」
確かに闇が動いた。立っていることができなかった。
「マントラって?」
「呪文よ」
「呪文??」
「とみにいちゃんこそ、カモノタダユキなんて、どうしたの」
「どうしたって・・・ここに立っていただろ、ついさっき」
「そんなの、いないわ」
祐子がほのかな光に笑った。
「まやかしを見たのね」
「やめてくれよ・・祐子まで・・」
祐子はあぐらを解き、立ち上がった。スカートに付いた土を払いヘルメットをかぶった。
「さ、帰りましょう。入口開けたままだしね」
祐子はスタコラと歩き出す。富五郎は慌てて追った。闇に取り残されるわけにはいかない。
帰りはすぐだった。所詮、たった二十歩の距離なのである。
ところが好古洞に出て驚いた。
日がとっぷりと暮れているのだ。時計を見ると、なんと6時間も経っている。
そんなに眠っていたのか??
富五郎はいぶかしがったが、祐子は懐中電灯を地面に照らしながらシャカシャカと動いている。祐子が言った。
「ふたしちゃってよ。重いから、とみにいちゃんお願い」
「お、おう」
富五郎は石のふたを元あった場所へ引っ張り出してはめた。
祐子は下草を適当に乱し、チェーンも隠す。
「やっぱり隠すんだな」
富五郎の独り言とも質問とも取れない言葉に祐子は反応せず、「こんどはサーチライト持ってこよう。しっかり探検しないと」と言ったのだ。
「サーチライトもいいけどさ・・」富五郎は言った。「祐子、さっき言ったよな、俺のこころが見たって・・あれはどういうことだよ」
「たぶんだけどね」
「たぶん?」
「わたし達、瞑想に誘われたのよ」
「瞑想だって?」
「ここはアシュラムかもしれない」
「・・・何だよ、それ」
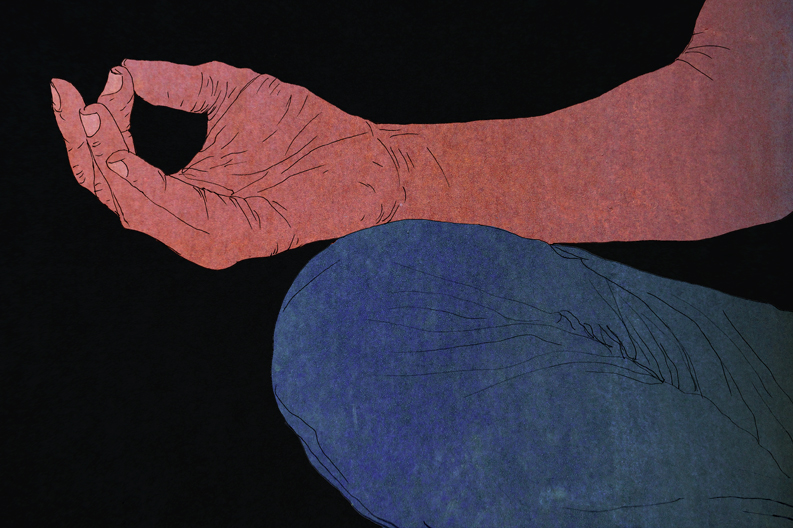
「瞑想の空間。眠ったような、眠っていないような、現実のような、夢のような・・・どこか遠いところへ連れて行かれた。そんな感じにならなかった?」
祐子におもむかれるままハム・サ、と呼吸を続けたとき、確かにその感覚が訪れた。
「そうだな、そうかも。そんな感じのとき、カモノタダユキが立っていた。でも、それって、なんなんだい・・」
「瞑想ってなかなかむずかしくてね、修行しなくちゃならないんだけど、アシュラムでは誘われるように瞑想に入れるのよ。もちろん誰でもってわけじゃなくて、ちょっとした才能は必要。インドにはそんな場所がたくさんあるらしいわ」
「この洞窟がその場所だっていうのか?」
「ま、アシュラムというのは例えだけどね」
謎だらけの話である。
「でも、祐子はどうしてそんなことを知ってるのさ。今までそんな話、全然しなかったじゃないか」
「八雲神社でね、何回かそういう体験をしたの。神社が私を乗せて宇宙へ飛び立っていく。ふわふわした、とてもくつろいだ気持ち。でも、この洞窟の力はふわふわしたものじゃない。ダイナミックだったわ。地下の磁場と八雲の力が洞窟で合わさったのかもしれない」
富五郎にはさっぱりわからない。富五郎は言った。
「カモノタダユキの姿はいやにはっきりしていたぞ。でもあれ、本物なのか?」
「さあ、それはわからないわね。私には見えなかったし」
「・・」
「私はとみにいちゃんとは別の場所へ連れて行かれたのよ。カモノタダユキは現れなかったけど、私はすべての道へ通じる交差点のような場所にいた。目の前にすべて道が光の筋となって見えたの」
祐子の表情が逆光で暗い。しかしその目は暗闇に飛ぶコウモリのように黒々とした光を帯びているようだ。
「洞窟のいっちばん上まで、ぜんぶ見えたのよ。ねえ、洞窟のてっぺん、どこへ続いていたと思う?」
「どこへだって? そんなのわかるはずないじゃないか」
祐子は、ふふ、と小さな笑い声を漏らした。
「では、ゲストのみなさま、ヒントを差し上げましょう、スリーヒントコーナーです」
「なんだ? 連想ゲームか」
「第一のヒントです。庭の医者」
「庭の医者って、カモノタダユキか・・・」
「質問はできません。では第二のヒントです。てっぺんは、ここから南東の方角」
「南東で、てっぺんで、カモノタダユキだって・・・ん?」
「三つ目のヒントは要らないみたいね」
「浄光明寺か」
上り下り列車が同時に発車し、一瞬ホームから人影が消えた。
闇夜に一声カラスが鳴く。
無人の北鎌倉駅は怪しい光に満ちていた。

次号へつづく





